配偶者ビザを自分で申請する完全ガイド
日本での生活を続けるためには、在留期限内に「配偶者ビザの申請」を完了させる必要があります。配偶者ビザを自分で申請したいと考えている方へ。本ガイドでは、「自分で手続きする人」が迷いやすい期間、必要書類、申請手順、書き方のコツまで網羅し、最後にセルフチェックリストと無料サポート窓口を提示します。
結論から申し上げますと、配偶者ビザの自力申請は可能です。多くの方が配偶者ビザの申請を自分で行い、費用を抑えています。ただし、書類不備などによりやり直しになる例も見られます。入管は個別事情を総合的に審査するため、証明書類や説明の不足は不許可の理由になり得ます。費用を抑えつつも失敗を避けたい方は、まず全体像を把握したうえで進めるのがおすすめです。
自分で配偶者ビザ申請を行うメリット・デメリット
配偶者ビザを自分で申請することを検討する前に、メリット・デメリットを正確に把握しましょう。多くの方が「費用節約」を理由に自力申請を選択しますが、実際には時間的コストや失敗リスクも考慮する必要があります。
メリット①費用を抑えられる
行政書士へ依頼する場合は報酬が発生しますが、自分で申請すれば報酬分を節約できます。なお、初回で日本国外から呼び寄せるときに利用される在留資格認定証明書交付申請(COE)には手数料がかからない一方、日本国内での在留資格の変更・在留期間更新には手数料が必要です(2025年4月以降、窓口申請6,000円/オンライン申請5,500円)。
参照:出入国在留管理庁「在留手続等に関する手数料の改定について」/同「在留手続等に関する手数料の改定」詳細
メリット②手続きの進捗を自分で管理できる
自力申請では入管とのやり取りを直接行うため、追加資料の提出や問い合わせなどを自身のスケジュールで進められます。途中で不安を感じた場合に、以降の工程だけ専門家へ相談・依頼する方法もあります。
デメリット①書類不備によるやり直しリスク
申請書の記載ミスや添付漏れ、説明不足などがあると、補正や再申請が必要になることがあります。特に「理由書」「質問書」などの作成は、事実関係を客観的に整理し、審査の観点に沿って記載する必要があるため、一般の方には負担が大きく感じられることがあります。
デメリット②最新要件のキャッチアップが必要
入管実務は様式や運用が見直されることがあります。最新の書式や必要資料を確認し、個別事情に応じて適切な根拠資料を選ぶ必要があります。
配偶者ビザは自力で申請できますか?要件・条件を解説
「配偶者ビザは自力で申請できますか?」という疑問に対して、基本要件を満たしていれば自力申請は可能です。複雑な事情がある場合は、早い段階で専門家へ相談すると安心です。
申請資格と必要要件の一覧
配偶者ビザを自分で申請する際に、一般的に確認される主なポイントは以下のとおりです。
- 日本人配偶者の戸籍謄本が取得可能であること(婚姻事実の記載が必要)
参照:出入国在留管理庁「日本人の配偶者等(必要書類)」 - 同居実態を示す住民票等があること
- 生計維持能力が確認できること(具体的な金額基準は公表されていません。課税・納税証明書、雇用・収入資料、預貯金の状況などを総合的に確認)
- 婚姻の真正性を立証できる資料(交際から婚姻に至る経緯の説明、写真、通信履歴など)
対象在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者・特別養子・日本人の子として出生した者が該当します。事実婚や同性パートナーシップはこの在留資格の対象外とされています。
参照:出入国在留管理庁「日本人の配偶者等(概要)」
配偶者ビザの必要書類と費用の全容
配偶者ビザの申請を自分で行うときは、必要書類の漏れがないか丁寧に確認しましょう。以下は代表的な例です。詳細や最新の様式は必ず公式サイトで確認してください。
提出書類の代表例(日本人の配偶者等)
- 在留資格認定証明書交付申請書(初めて日本へ呼び寄せる場合)/在留資格変更許可申請書・在留期間更新許可申請書(日本国内での変更・更新の場合)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 申請人の国籍国の婚姻証明書(翻訳を含む場合あり)
- 住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
- 課税(所得)証明書・納税証明書、在職証明書など収入・生計関係資料
通帳のコピーは法律上の一律必須ではありませんが、生計維持能力の補足資料として求められる/提出を勧められることがあります(特に収入が不安定な場合など)。提出要否は状況により異なります。
申請料はいくら?費用の考え方
費用は申請の種類で異なります。初回の在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料なし、日本国内で行う在留資格の変更・在留期間更新は手数料が必要です(2025年4月以降:窓口申請6,000円/オンライン申請5,500円)。別途、戸籍・住民票・証明写真などの取得費用がかかります。
参照:出入国在留管理庁「手数料の改定」
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 手数料なし(証明書取得費等は別途) |
| 在留資格の変更・在留期間の更新 | 窓口6,000円/オンライン5,500円 |
| 証明写真 | 500〜1,000円程度 |
| 戸籍謄本・住民票 | 各数百円(自治体により異なる) |
| 課税・納税証明書 | 各数百円(自治体により異なる) |
書類作成のポイント(不備防止)
- 黒のボールペンで記入(消えるペンは不可)
- 訂正は二重線+訂正印(修正液・修正テープは不可)
- 空欄は「なし」「該当なし」と記入
- 日付は西暦で統一
- 署名・押印漏れの最終チェック
- 「質問書」「理由書」は事実関係を客観的に、簡潔に記載
自分で配偶者ビザを申請する手続きの流れ
申請書類の入手・作成
申請書類は法務省(出入国在留管理庁)のサイトから入手できます。最新版を使用してください。
- 法務省 出入国在留管理庁にアクセス
- 「申請書等ダウンロード」→該当する申請(認定/変更/更新)を選択
- 「日本人の配偶者等」用の様式をダウンロード
- A4で印刷(両面不可)し、丁寧に記入
書類作成・収集には1〜2週間程度を見込むと余裕をもって準備できます(個別事情により増減)。
入管窓口での申請手順(例)
- 受付(各局の受付時間に従う)
- 書類確認・整理番号の発行
- 受理・処理期間の案内
持参物の例:申請書類一式、本人・日本人配偶者の身分証、委任状(代理申請の場合)、訂正用の印鑑など
結果通知までの期間とフォローアップ
処理期間は案件により異なります。入管庁は全国の平均処理日数を定期的に公表していますので、最新情報の確認をおすすめします。一般的には1〜3か月程度かかることが多く、追加資料の提出が生じた場合はさらに時間を要します。
参照:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
結果通知の例:
- 許可:在留資格認定証明書の交付(COEの場合)または在留カードの更新・変更
- 不許可:理由が記載された通知書
- 追加書類:電話や郵送・連絡票などで指示
追加提出を求められた場合は、指定期限内に対応しましょう。
自分で配偶者ビザ申請する際のよくある質問
Q. 自分で申請を進める基本ステップは?
STEP 1:必要書類の準備(目安:1〜2週間)
- 申請様式のダウンロード・記入
- 戸籍・住民票などの取得
- 収入・生計関係資料の準備
- 婚姻証明書の翻訳(必要時)
STEP 2:入管窓口で申請(目安:1日)
- 管轄入管の受付時間を確認し来庁
- 面談対応(指示があった場合)
- 受理票の受領
STEP 3:審査・結果受領(目安:1〜3か月)
- 追加書類の提出
- 許可通知の受領(COE交付または在留カードの更新/変更)
全体としての作業時間は人によって差がありますが、書類作成・収集、補正対応まで含めると相応の時間を要します。
Q. 不備があった場合は?
軽微な不備:電話・書面で指示された追加資料や訂正を期日までに提出すれば、審査継続されるのが一般的です。
重大な不備:不許可となることがあり、内容を踏まえて再申請を検討します(変更・更新の再申請には上記の手数料が再度必要)。
Q. ブログ情報だけで進めても大丈夫?
ブログや一般サイトは参考になりますが、実際の審査は個別事情を総合的に判断します。過去に不許可歴がある、収入が不安定、年齢差が大きい、出会いの経緯の説明が難しい、日本語の読み書きが不安などのケースでは、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。
配偶者ビザを自分で申請するときのまとめ
自力申請が向いている方
- 十分な準備時間を確保できる
- 書類作成が得意、または丁寧に進められる
- 標準的なケースである
- 不許可時のリスク(時間的ロス等)も踏まえて判断できる
専門家サポートを検討したい方
- 確実性を高めたい
- 時間的制約が厳しい
- 過去に不許可歴がある
- 事情説明が複雑になりやすい
「費用を抑えたい」だけで自力申請を選ぶと、書類不備による遅延で生活設計に影響が出ることもあります。状況に応じて、無料相談などを活用して最適な進め方を選びましょう。
当社では配偶者ビザ申請の無料相談サービスを提供しています。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請方法をご提案します。配偶者ビザを自分で申請するか、サポート依頼をするか迷っている方も、お気軽にご相談ください。
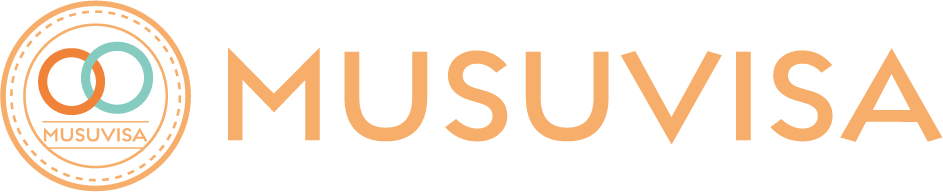
コメント